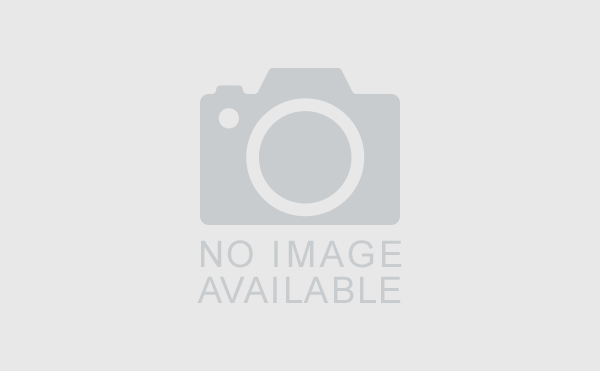東京都内では駐車場設置は義務!?【不動産鑑定士が解説します】

地価が高い東京の都心部において駐車場はあまりコスパの良い土地・建物の利用方法ではないのですが、店舗・事務所ビルなどの特に大規模なものを中心に駐車場を設置しているケースがあります。
もちろん商業施設などにとっては駐車場は集客に役立つというのもありますが、都内は比較的電車網が発達していて運行本数も多いです。
一方、道路は渋滞することが多く駐車料金も高い、車が必要な場合でも流しのタクシーがつかまえやすい、日中の人口流入は通勤・通学の方々が中心なので公共交通機関の利用が主となる、などの理由から車の利用は業務用車両が中心となり個人のマイカー利用はさほど多くありません。
ではなぜ駐車場があるのかと言うと、東京都の条例で建物に駐車場の設置が義務付けられているからです。
この条例の背景には、マイカー利用が少ないとは言っても業務用車両は多く、駐車場が少ないと路上駐車などが横行して交通渋滞をさらに悪化さたり交通の安全に支障をきたしたりして都市機能を損ねてしまうため、快適な街づくりには駐車場の供給・整備が不可欠だという都市計画上の配慮があります。
そこで以下、建物に駐車場の設置を義務付けている東京都駐車場条例の大まかな考え方を解説します。
東京都駐車場条例
詳細に立ち入ると全体像がわかりづらくなってしまうので大ざっぱにとらえると、人や車が集まりやすいエリアの人や車が集まりやすい用途の建物についてはより多くの駐車場台数の設置が求められています。
エリアで言うと人や車が集まりやすい商業地域、近隣商業地域、そしてより駐車場のニーズが高いということで指定された駐車場整備地区が設置台数の要請が高くなっています。
逆に住居系や工業系の地域、駐車場整備地区に含まれないエリアはより設置台数の要請が低くなっています。
また、同じ商業地域内にあっても不特定多数の人たちや車が集まる建物用途、例えば店舗・事務所・ホテル・病院などは設置台数の要請が高く、特定少数の人や車しか集まらない建物用途、例えば住宅は設置台数の要請が低くなっています。
「あれ、うちのマンションは商業地域にあるけど駐車場がないぞ」
と思われる方もおられるかもしれませんが、建物の規模により駐車場を設置する義務の有無が決まってきます。
具体的には、商業地域・近隣商業地域・駐車場整備地区では店舗など不特定多数の人や車が集まりやすい用途(特定用途といいます)の面積に、住宅など特定用途以外の用途の面積×3/4を足した面積が1,500㎡を超える建物は駐車場の設置が求められますので、これより小さければ設置は任意となります。
ですから先ほどの商業地域にあるけど駐車場のないマンション、例えば建物が全て住宅で住宅部分の面積が合計で1,600㎡であれば、その3/4は1,200㎡となり条例で駐車場設の置義務が有るか無いかの分かれめである1,500㎡を下回りますから駐車場設置の義務はありません。
どのような用途が特定用途に含まれるかは条例で個別具体的に決められています。
また、どうしても建物の敷地内に駐車場を設置するのが困難な場合には近隣に駐車場を確保することが認められます。
まとめ
地価が相対的に高い東京で収益性の低い駐車場を建物の敷地内に設置するというのは経済不合理となり、市場原理にまかせていては駐車場の設置は進みません。
一方、都内は業務用車両の通行が多く駐車場不足と相まって車が路上駐車されることも多く交通渋滞を悪化させる一因となっています。路上駐車が増えれば運転者からの見通しも悪くなり人の飛び出しによる事故などのリスクも増えてしまいます。
そこで、より快適な街づくりを進めるために都が条例によって、人や車の集まりやすいエリアの人や車が集まりやすい建物を中心に駐車場の設置を義務付けることによって駐車場の供給を促進しているのです。