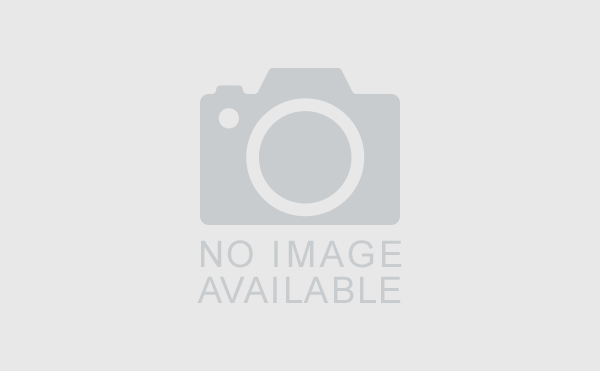用途地域はなぜ決めるのか?【不動産鑑定士が解説します】

物件を探しているときに不動産屋さんから「用途地域」という言葉を聞いたことがあるかと思います。
どのような建物を建てることができるかを13パターンに分類したもので、都市計画法で決められています。
これら13の用途地域の内容についての説明はネットで検索すれば多数ヒットしますので割愛して、
- なぜこのようなものが決められているのか
- 具体的にどういうメリットがあるのか
を解説します。
用途地域はなぜ必要か
土地計画法の目的は住みよい街づくりです。そのために、「都市計画区域」というものを定めて、その区域内では秩序立てた街づくるが行われるようにしています。
ある場所に住宅地域が広がっていたところ、突然大きなショッピングセンターや工場ができたら住環境はどうなるでしょうか?
実際にこのようなことが高度成長期と呼ばれる今からだいたい50~60年前に起こったために、諸外国を見習って地域ごとに建てて良い建物と建ててはならない建物を建物の用途によって指定する用途地域制が導入されたのです。
用途地域の分類と特徴
用途地域は大まかに分けて住居系、商業系、工業系に分類できます。
そして集積度、つまりどれだけ建物が密集して高く建っているかという度合いは、住居系が低く商業系で高くなって工業系でまた低くなる、という風になっています。
住宅はあまり密集して建っていると通風・日照やプライバシーなどの生活環境が悪くなってしまいます。
また、工場では高熱を扱ったりすることもあるのであまり密集していると防災上望ましくないうえ、大きく重たいものを流れ作業で作る工程を考えると高層だと原材料などを階層間で移動することとなり非効率になるから高集積化のニーズも少ないのです。
一方、商業用途の建物つまり店舗や事務所においては、むしろ密集していた方が効率が上がりますし、工場のように数百度とか千度以上の熱を扱うこともあまりありません。
なので集積度は住居系が低、商業系が高、工業系が低、となっています。
具体的メリット
こように地域ごとに建てることができる建物を建物用途によって制限することでどんなメリットがあるのでしょうか?
道路
例えば工業用途の建物しか建てられない用途地域においては工場などが建ち並ぶことになりますので、原材料や製品を大型トラックやトレーラーで搬送できるように道路もある程度広い必要があります。
逆に、居住用途の建物しか建てられない用途地域においては、通行が予想される車両は普通乗用車やバスなのでそれほど広い道路は必要なく、むしろあまり道路が広いと通り抜け車輛が増えて騒音や危険が増すなどの不都合が生じることとなります。
道路は通常国・都道府県・市区町村が作って管理しますので税金が使われます。地域ごとに建てられる建物の用途が決まっていればそれに道路の仕様を最適化することで税金を有効に使うことができます。
ガス
また、ガスなどのインフラも高圧・中圧管は工業系の用途地域に埋設し住宅系の用途地域は低圧管のみを埋設すれば投資が効率的になります。
ガス料金は、ガス会社が投資額などの事業に投下された諸経費に適切な利潤を加算した額を回収できるような水準に設定される*ので、無駄な投資はガス料金に跳ね返ってきます。
*包括原価方式といいます
なのでガス会社の投資が効率的かどうかは皆さんの生活にも影響することとなるのですが、その投資を効率化するのにも用途地域は一役かっているのです。
学校
住居系の用途地域においては住居が建ち並ぶことが想定されますが、そうなるとそれに見合った学校などの教育施設も必要になります。
全国的には人口は減少・年齢分布は高齢化に向かっていますが、東京都では人口の流入が続いますのでそれに見合った教育施設(特に義務教育施設)をどのように手当てしていくかは都市計画上の重要な課題となります。
最近は首都圏では人口流入を促すために住居系の用途地域で高層建物の建築をより許容する方向にありますが、教育施設や上下水道・交通網の整備等との整合性を検討して計画的に高層建物の建築を進めるような用途誘導をしないとかえって住みづらい街となって人口の流出につながってしまいます。
まとめ
用途地域があることによって、住環境が守られるなどの直接的な恩恵はもちろんのこと、効率的な街づくりを進めることができるようになり各インフラへの税金の最適配分などを通じて多くの人たちの利益に役立っていることがご理解いただけたと思います。