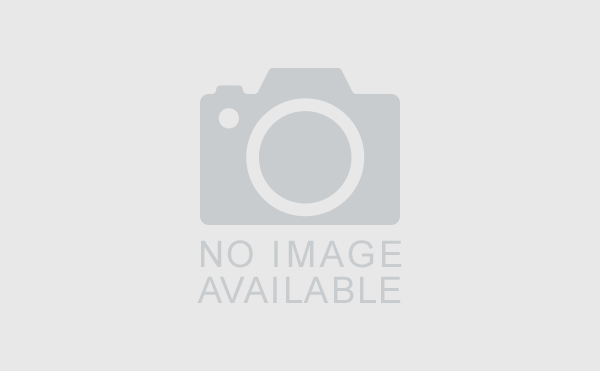市街化調整区域の土地に建物を建築できるか?【不動産鑑定士が解説します】

相続した土地や割安な売り物件が市街化調整区域にあり建物が建築できないと聞いたがこれは本当なのか?例外は認められないのか?できれば簡単な調べ方ががあれば知りたい、などと考えていませんか?
この記事では、鑑定歴20年以上の不動産鑑定士が以下の内容を解説します。
- 市街化調整区域にある土地に建物の建築が可能な場合
- 建物建築の可否を自分で調べる方法
市街化調整区域にある土地に建物の建築が可能な場合
市街化調整区域にある土地については、原則として建物の建築が禁じられています。「市街化」すなわち建物が連なるなどして市街地と化していくことを「調整」つまり抑制すべき区域だからです。
ただし、全ての原則がそうであるように例外があります。
開発許可を得れば建物は建築可能
市街化調整区域にある土地であっても開発許可を得れば建物を建築することができます。
開発許可とは、土地の区画形質の変更の際に必要とされる許可を指します。区画の変更とは一団の土地に道路を通すこと、形質の変更とは切土・盛土のことです。
なので土地の区画形質の変更をしなければ開発許可は必要ないのですが、市街化調整区域において建物を建築する場合には土地の区画形質を変更しない場合であっても開発許可の申請が義務付けられています。
建物の建築に先立って開発許可の申請を求めることで、建物が建ち並んで市街化が進んでしまわないように睨みを利かせているのです。
どのような場合に許可されるか
市街化調整区域における開発許可の要件は都市計画法の第33条、第34条に規定されています。一読しただけでは何のことかわかりにくい上に、熟読して理解したところで建築が認められる建物は限定的ですので「ああ、これだったらやっぱり無理だ」と思ってしまうかもしれません。でもまだ諦めないでください。
実際の運用は地方自治体の裁量による
国が全てを画一的に決めてしまうと地域の実情に即した政策運営ができなくなるため、市街化調整区域内の土地における建物の建築の可否に関する実際の運用については地方自治体の裁量が認められています。
この点を、埼玉県久喜市の事例で具体的に見ていきたいと思います。久喜市を例として取り上げるのには理由があるのですが、これは後で説明します。
久喜市の事例
下が久喜市のウェブサイトの市街化調整区域に関するページです。
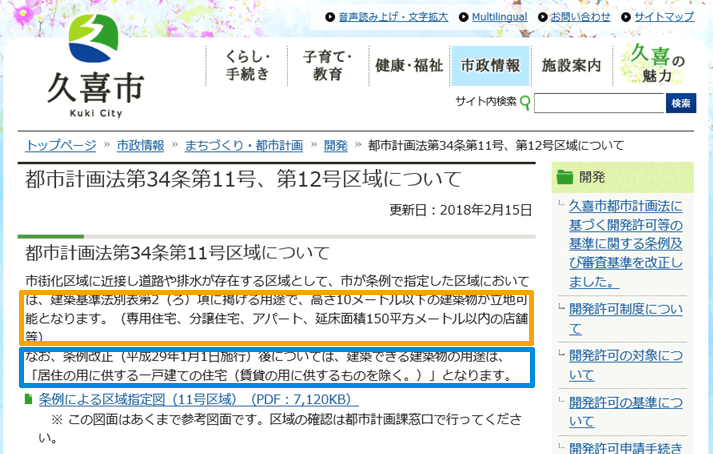
市街化区域に近接するなどの要件に基づき市が指定した区域においては、オレンジ色の枠内に例示されている建物を建築することができるのがわかります。
ただし、その下の青色の枠内の記載を見ると、条例の改正により平成29年1月1日以降は建築可能な建物の用途が「居住用一戸建て住宅」に限定され、それまで建築することができたアパートや小規模店舗は除外されたことがわかります。
つまり、土地を買ったときや相続した時に建てられたはずの建物であっても時間が経過すれば建てられなくなる場合がある、ということは強く意識しておく必要があります。
このことを示したかったので、久喜市の例を使ったのです。
建物が建築可能か自分で調べる方法
それでは市街化調整区域にある土地に建物を建築することができるかどうかを自分で調べる方法を解説します。
資料を集める
市街化調整区域に関する調査は役所で行いますが、その前に以下の資料を収集しておくことが望ましいです。
インターネットで収集した情報
先ほど久喜市の例を示しましたが、市街化調整区域の情報は市区町村のウェブサイトで集められることが多いです。なのでまずインターネットで情報を収集します。
基本的なことですが、自分が調べようとしている土地がそもそも本当に市街化調整区域にあるのかということも再度確認します。売り物件は不動産屋さんが調べているでしょうが、相続した土地などは不動産屋さんは関与していないではないでしょうから記憶違いということもあります。
インターネットの検索キーワードに「○○市」+「都市計画図」などと入力するとだいたい都市計画図を表示するサイトがわかります。都市計画図を開けたら、自分の調べている土地が間違いなく市街化調整区域にあるか確認します。
また、久喜市のようにどのような建物が建築可能かがあらかじめ示されていれば、これを印刷して持参すると担当官の言うことがウェブの情報と違う場合に「ウェブサイトにはこう書いてあるんですけど、なんで違うんですか?」と質問できたりして便利です。
地図
土地の全部が市街化調整区域内にあるのか一部のみなのか、市街化調整区域と言っても部分部分で規制が異なる場合どの部分に該当するのか、といったことを確定するのに必要です。YahooやGoogleの地図でも構いません。
公図
土地が市街化区域と市街化調整区域のちょうど境目にあるような場合に、役所が公図に境界を書き込んで管理している場合があるため、公図を持参しておくと便利です。法務局またはインターネットで取得できます。
登記事項
土地の地目が「田」「畑」等の農地である場合には別途農地法の規制がかかる場合がありますので、地目の確認のために必要です。これも法務局またはインターネットで取得できます。
担当窓口を電話で確認する
電話をかけるのは市町村または区役所です。「市街化調整区域について調べたいのですが、担当部署はどちらになりますか?」と聞けば教えてもらえます。通常は都市計画課、まちづくり推進課といった部署になります。役所によっては庁舎が複数ある場合がありますので、どの庁舎の何階にあるか教えてもらっておくと迷いません。また、調べようとしている土地が農地の場合には農業委員会も聴聞の必要が生じます。
登庁して確認
実際に登庁して、土地を特定したうえで建物の建築が可能かどうか、可能な場合どのような建物用途であれば認められるのか、そのためにはどのような手続きが必要なのか、一般にどれくらいの時間と費用がかかるのかを確認します。
まとめ
以上、市街化調整区域にある土地でも建物の建築が可能な場合があることと、どのようにすればそれを自分で調べることができるかについて解説しました。
ただ、もしもお仕事がおありで平日の営業時間に役所に登庁できない場合などに、電話で対応してもらえるかというとこれはなかなか難しいです。担当官としては、地図を示してもらうなどして「場所がここで間違いない」という確認をとらないと、自信をもって正確な対応ができないからです。
「自分で調べるのはちょっとハードルが高い」「調べてみたいけど平日時間が取れない」といった方は、ご遠慮なくお問い合わせページよりご相談ください。